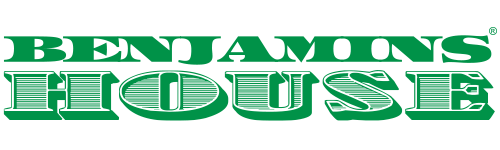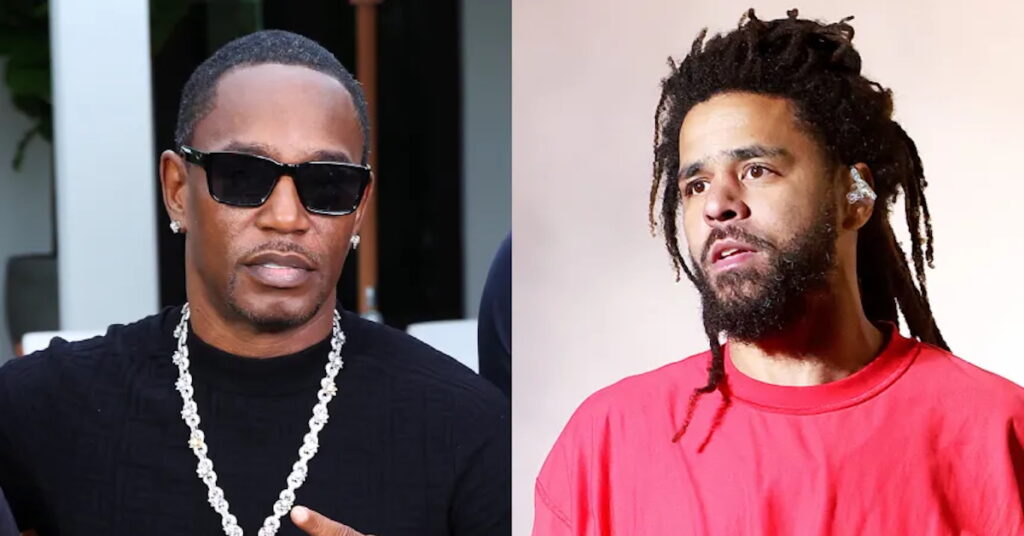Durk側の弁護団は「陪審に不当な偏見を与える」と主張
アメリカ連邦検察は、今後予定されているLil Durkの殺人依頼に関わる裁判において、彼の歌詞やミュージックビデオ、関連する映像表現を証拠として使用することを禁じるよう求めたLil Durk側の要請を退けるよう、裁判官に強く求めている。検察は、これらの資料が陪審員に不当な先入観を与えるという主張に真っ向から反論している。
裁判資料によると、検察側は、被告本人の言葉や映像作品を排除することは、彼が直面している容疑と直接関係する重要な証拠を陪審が評価する機会を不当に制限することになると主張している。
本名Durk Devontay BanksことLil Durkは、ラップ界のライバルであるQuando Rondoに懸賞金をかけたとされる計画を主導したとして告発されている。この計画は、2022年にロサンゼルスで起きた銃撃事件につながり、Quando RondoのいとこであるSaviay’a “Luh Pab” Robinsonが死亡したとされている。
検察によれば、この計画は、2020年11月にアトランタのラウンジ外でQuando Rondoとの口論の末に死亡した、Lil Durkの親友でありOnly the Family(OTF)所属アーティストでもあったKing Vonの殺害への報復として動機づけられたという。
検察は、Lil Durkの意図、動機、そしてOTF内での指導的立場を示すものとして、複数のミュージックビデオや音源を証拠として提出している。そこには、Saviay’a “Luh Pab” Robinson殺害の2か月後に公開された「Risky」のMVや、「AHHH HA」、「Rumors(feat. Gucci Mane)」、「Hanging with Wolves」といった楽曲の歌詞が含まれている。
さらに、共犯者とされるDeandre Dontrell WilsonことDeeskiが参加している複数のLil Durkの楽曲も、検察側の証拠として提出された。
裁判資料によると、Lil Durkの歌詞の一部は、問題となっている暴力行為や、ライバルに対する行為への資金提供や指示に関与したとされる彼自身の立場を示唆しているとされる。その一例として、Nardo Wickの「Who Want Smoke?? (Remix)」でのLil Durkの冒頭バースが挙げられている。
「“Vonのために仕返ししろ”って俺のページで言ってくる、あいつらは分かってて煽ってる/血で血を洗う形で取り返した、やり方ってのはそういうもんだろ」
この楽曲には21 SavageやG Herboも参加している。
検察は、こうした歌詞が、Lil DurkがOTFのリーダーとして共犯者たちの暴力行為に資金を提供し、懸賞金をかけていたという主張を裏付けるものだと述べている。
また、共犯者の携帯電話から見つかったとされる、Boonie Moをフィーチャーした未発表曲「Scoom His Ass」も証拠として挙げられている。この楽曲はRobinson殺害前後の出来事を示唆しているとされる。
歌詞には次のような一節が含まれている。
「カリフォルニアで走り回り、ビバリーヒルズを銃を積んで通過/バウンティ・ハンター」
連邦当局は、Robinsonが射殺されたビバリー・グローブのガソリンスタンドがビバリーヒルズの近くに位置している点を指摘している。
検察側は、これらの資料を陪審に提示できないようにすることは司法プロセスを損なうものであり、被告自身の言葉を評価するという陪審の役割を弱めることになると主張している。特に、それらの言葉が起訴されている共謀と直接結びついていると政府が考えている以上、排除されるべきではないとしている。
一方、Lil Durk側の弁護団は1月にこの申し立てを行い、提出予定の証拠は「極めて大きな不当な偏見を生む危険がある」と主張した。さらに、政府は導入しようとしている音楽作品について十分な文脈説明をしていないとも指摘している。
「(どの音楽的証拠を使うかについての)通知には、誰が歌詞を書いたのか、いつ作られたのか、被告がそれを採用したのか、また政府がそれぞれの歌詞を争点となっている事実とどのように結びつけているのかが示されていない」と弁護側は述べている。
「こうした基本情報がなければ、その音楽証拠が起訴された共謀と時間的に関連しているのか、あるいは“時間的に離れすぎている”のかを裁判所は判断できない。」
Lil Durkは2024年10月にフロリダで逮捕されて以降、現在も勾留されている。マイアミ国際空港近くで、複数の国際線航空券を予約していたと当局が発表し、国外逃亡の恐れがあると判断されたためだ。彼は保釈なしで、裁判を待つ身となっている。